住宅の雨漏りというと、多くの方は屋根の上や外壁のヒビ割れを思い浮かべるかもしれませんが、実は「軒天」も非常に雨漏りが多い箇所の一つです。軒天とは、屋根の張り出しの裏側にある天井部分のことで、建物の構造を守るためにとても重要な場所です。しかしながら、普段はあまり目に触れることのない位置にあるため、劣化や損傷が見逃されやすく、気づいた時には天井や屋根裏まで水が回っていたというケースも少なくありません。
本記事では、「軒天 雨漏り」に関して、原因、調査のポイント、交換工事の流れ、工法の種類、さらに最近注目されている有孔ボードの活用方法について、分かりやすく詳しく解説します。雨漏りのリスクが高まる台風シーズンを前に、住まいの安全性を守るためにも、軒天の正しい知識と対応方法を知っておきましょう。
軒天とは?住宅の中での役割と構造を理解する

軒天とは、建物の外壁から突き出した屋根の裏側にある「天井」にあたる部分を指します。ここは見た目では単なる装飾のように感じるかもしれませんが、実際には風や雨から外壁や屋根の接合部を守る重要な役割を果たしています。また、屋根裏の通気を確保し、屋内の湿気を排出するための通気孔が設けられることも多く、住宅の耐久性を保つうえでも大きな意味を持っています。
軒天の材料は、木材、ケイカル板、スレート板、アルミパネルなどが用いられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、たとえば木材は見た目の質感がよい反面、水に弱く腐朽しやすいという特徴があります。一方、金属系やケイカル系の素材は耐水性に優れていますが、劣化が進むと表面が割れてしまうこともあります。
また、近年では防火性能を高める目的や通気性を確保する目的で、有孔ボードを用いた軒天施工が多く見られるようになっています。これにより、住宅の天井裏から水分を効率よく逃がし、雨漏りの予防に役立てることができます。
軒天の雨漏りで多い原因とは?構造的リスクを把握する

軒天からの雨漏りの原因で特に多いのが「経年劣化によるひび割れ」や「腐食」です。とくに築年数の経った建物では、軒天材が紫外線や風雨にさらされ続けたことで防水性能が落ち、水分を吸収しやすい状態になっていることがあります。この状態で大雨や台風に見舞われると、一気に水が浸入し、天井裏にまで雨水が到達してしまうのです。
また、屋根や外壁との取り合い部分のシーリング材が劣化していることも雨漏りの原因になります。軒天は複数の構造体の接合部にあたるため、ちょっとしたズレや隙間でも水の侵入が起こりやすいのが特徴です。
さらに、屋根の勾配が不十分で水がうまく排出されなかったり、雨樋が詰まって雨水が溢れてしまったりと、排水機能に問題があるケースもあります。屋根カバー工法などで屋根だけを施工した結果、通気が不足して湿気がこもり、軒天の裏側に結露が生じて雨漏りと似た現象が起きることもあります。
こうした現象は、住宅の構造全体に関わる問題であり、軒天の一部を補修するだけでは根本的な解決にならない場合もあるため注意が必要です。
軒天の構造と屋根裏との関係性について
なぜ軒天が雨漏りの発生源となるのか?屋根裏とのつながりに注目
軒天は単なる外装の一部に見えますが、実は屋根裏や小屋裏と密接に関係している構造上の重要部位です。屋根裏は湿気や熱がこもりやすく、そのままにしておくと結露が発生し、軒天にまで水分が伝わることがあります。この湿気が素材に染み込むことで、内部から腐食やカビの原因になることも少なくありません。さらに、屋根裏の通気が確保されていないと、気温差によって水滴が発生し、それが徐々に軒天裏に垂れてきて「雨漏り」のような症状を起こすこともあります。
特に近年の高気密住宅では、内部の空気が外に出にくい構造になっているため、軒天からの排湿ができていないと、湿気の逃げ場がなくなってしまいます。これが、目に見える雨水の侵入ではなくても、天井裏に湿気が溜まり、それが軒天の裏に悪影響を与えているパターンです。軒天と屋根裏は独立しているように見えて実は一体化しており、この点を理解することが、原因の特定と正確な修理につながります。
雨漏り箇所の調査と確認の方法

軒天からの雨漏りを止めるためには、まず「どこから」「なぜ」水が漏れているのかを正確に突き止めることが最も重要です。このために行われるのが専門業者による「調査」と「確認作業」です。
調査では、目視によるチェックのほか、必要に応じて赤外線サーモグラフィーや散水試験、ドローンによる屋根撮影などの方法が取られることもあります。軒天の雨漏りは単体で発生しているように見えても、屋根の葺き替えが不完全だったり、カバー工法が適切でなかったりすることで発生しているケースも多く、調査では屋根・外壁・樋・天井裏など広い範囲を確認する必要があります。
また、天井に水のシミが出ている場合は、軒天の裏側にまで水が入り込んでいる可能性が高いため、天井の裏の断熱材の湿り具合や構造材の腐食も併せて確認します。雨漏りというのは水の通り道が意外なところを通るため、原因箇所と症状の出ている場所が離れていることも多いのです。
ここでポイントになるのは、被害の“範囲”と“原因”をしっかり区別して考えることです。軒天の一部が濡れているからといって、必ずしもその真上の屋根から漏っているとは限りません。雨漏り対策は構造全体を把握した上での正確な調査と確認作業から始まります。

カバー工法と葺き替え工事の違いと軒天への影響

雨漏りの原因として、屋根そのものの問題も多く、特に「カバー工法」や「葺き替え」の工事内容が軒天に影響を与えている場合があります。カバー工法とは、既存の屋根材の上に新しい屋根材を被せる施工方法で、費用や工期を抑えられるメリットがある一方、屋根裏の通気や結露の対策が十分に行われていない場合、軒天や天井裏に湿気がこもりやすくなり、結果的に軒天から雨漏りが発生するリスクがあります。
一方、葺き替えは既存の屋根材をすべて撤去し、新たな防水シートや下地材を整えたうえで屋根を新設する工事であり、構造的に問題がある場合や雨漏りの根本解決を目指すときに適しています。葺き替えは初期コストが高くなるものの、軒天にまで水が回るような重大なトラブルを未然に防げる工法です。
軒天の雨漏りを見つけた際には、屋根工事が過去にどのように行われたかも含めて確認することが重要です。適切な工法が選ばれていないと、見えないところで雨水や湿気が滞留し、軒天材を劣化させる原因となってしまいます。
修理工法と有孔ボードの効果

軒天の雨漏りを防ぐための修理工法には、いくつかの方法があります。軽度な劣化であれば塗装や部分補修で対応できますが、構造材まで水が回ってしまっているようなケースでは、交換工事や下地の補強が必要です。
その際、注目されているのが「有孔ボード」を使用する工法です。有孔ボードとは、表面に小さな穴が無数に空いたボードで、軒天の通気と排水性能を高める目的で用いられます。雨水が溜まりにくくなり、また屋根裏の湿気をスムーズに外部へと排出できるため、結露やカビの防止にも効果があります。
この有孔ボードは施工時のポイントとして、通気の流れを妨げないように、正確な位置で取り付けることが求められます。施工不良があると、排水も通気も機能しなくなり、逆に水が溜まりやすくなってしまうこともあります。
さらに、シーリング材による防水処理や下地材の補強なども同時に行うことで、有孔ボードの効果が最大限に引き出され、今後の雨漏り再発防止につながるのです。
軒天材の種類ごとの特徴と雨漏りへの強さ
素材選びが耐久性を左右する。各材質の長所と弱点を比較
軒天に使われる建材は複数あり、素材ごとに耐久性や防水性、施工性が異なります。たとえば、木製の軒天は見た目の質感が高く、和風建築や高級住宅で多く採用されていますが、水分を吸いやすく、カビや腐朽に弱いため、雨漏りの原因になるケースが多いです。定期的な塗装や防腐処理が必要ですが、それでも長期間放置すれば劣化が進行します。
ケイカル板(ケイ酸カルシウム板)は耐水性や防火性に優れており、多くの住宅で標準仕様となっている素材です。ただし、施工時に隙間があるとそこから水が入り込む恐れがあるため、丁寧なシーリング処理が求められます。
近年では、有孔タイプのケイカル板や不燃ボードが人気を集めており、通気性と防水性のバランスが取れた施工が可能です。アルミやガルバリウム鋼板などの金属系素材も高耐久ですが、雨音が大きくなることや加工の難しさがネックになる場合があります。
素材選びを誤ると、たとえ丁寧に施工されていても数年で不具合が起きることもあるため、軒天の交換時には建物の気候条件や通気構造を踏まえて適切な素材を選ぶことが重要です。
軒天の交換工事と工事中の注意点

雨漏りが深刻で、軒天材が劣化・腐朽している場合には、軒天の全面交換工事が必要になります。交換工事ではまず、既存の軒天材を撤去し、構造材や天井裏の状態を確認します。水に濡れた木材はシロアリの被害を受けやすく、場合によっては補強や一部の交換が必要となることもあります。
次に、新しい軒天材を選び、施工していきます。最近では、ケイカル板や不燃パネルなど、耐久性・防火性に優れた素材がよく使われており、住宅の安全性が高まる傾向にあります。また、有孔ボードと組み合わせて施工することで、今後の水はけや通気性も改善され、結果として家全体の耐久性向上にもつながります。
交換工事の際に特に注意したいのは、「屋根や雨樋との接合部の処理」です。この部分から水が入りやすいため、シーリングや防水テープを適切に施工し、雨仕舞いを丁寧に仕上げる必要があります。工事は見た目のきれいさだけでなく、目に見えない部分の仕上がりが重要なポイントになります。
雨漏り後に天井裏・壁内部に及ぶ二次被害の実態

軒天からの雨漏りを「見た目だけで軽微」と判断して放置すると、実は内部で深刻な被害が進行していることがあります。水は重力に従って下へ流れるため、軒天から入り込んだ雨水が天井裏を通り、室内の天井材や断熱材を濡らし、やがて壁の内部にまで浸透するケースもあります。
こうした二次被害は目に見えない場所で進行するため、気づいた時にはクロスが剥がれたり、木材が腐っていたり、電気配線がショートしていたりと、大規模な工事が必要になることも少なくありません。漏水による木部の腐食や、鉄骨構造の場合にはサビによる強度の低下など、構造的な問題に発展することもあります。
また、湿った天井裏はシロアリやダニ、カビの繁殖を促す環境になりやすく、健康被害を及ぼす恐れも出てきます。特に、梅雨や台風の時期は被害の進行が速いため、少しでも異変に気づいたらすぐに調査を依頼することが大切です。
軒天のメンテナンスと台風後の対応

交換や修理が終わったとしても、軒天の雨漏り対策はそこで終わりではありません。日頃のメンテナンスによって、状態を良好に保つことが長期的な雨漏り予防につながります。
まず、年に一度程度の定期点検をおすすめします。特に、台風や長雨があったあとは、天井にシミが出ていないか、軒裏に黒ずみがないかをしっかり確認しましょう。有孔ボードを使用している場合は、排水孔が詰まっていないかを確認し、必要があればホースやブラシでやさしく清掃します。
また、軒天の表面が色あせたり、塗装が剥がれ始めた場合には、塗装を施して耐久性を保ちましょう。塗膜があることで水の浸透を防ぎ、素材の劣化スピードを抑える効果があります。塗料は防カビ・防藻機能付きのものを選ぶと、より長く美観と性能を保てます。
早期発見・早期対応が、軒天からの雨漏りを未然に防ぐもっとも効果的な方法です。
台風後の点検チェックリストと応急対応のポイント
台風後は必ず確認を!自分でできる簡易チェックの手順も紹介
台風のあとに軒天からの雨漏りが発覚するケースは非常に多くあります。暴風によって屋根材がずれたり、雨樋が詰まったり、飛来物で軒天が損傷してしまうことで、そこから水が浸入するというパターンです。
台風通過後には、以下のようなチェックポイントを確認しておきましょう。
- 軒裏に黒ずみや水滴、膨らみがないか
- 天井に新たなシミや変色が出ていないか
- 雨樋が外れていないか、排水口が詰まっていないか
- 軒天の継ぎ目や目地に隙間ができていないか
これらの点を目視で確認し、少しでも異常があれば早急に専門業者に調査を依頼しましょう。応急対応としては、防水テープやブルーシートでの一時的な覆いが有効ですが、あくまで一時しのぎであり、放置は厳禁です。
台風は建物にとって大きなストレスを与える自然現象です。被害の有無に関わらず、台風後は必ず家全体をチェックし、軒天も含めて細かい箇所を確認する習慣をつけておきましょう。
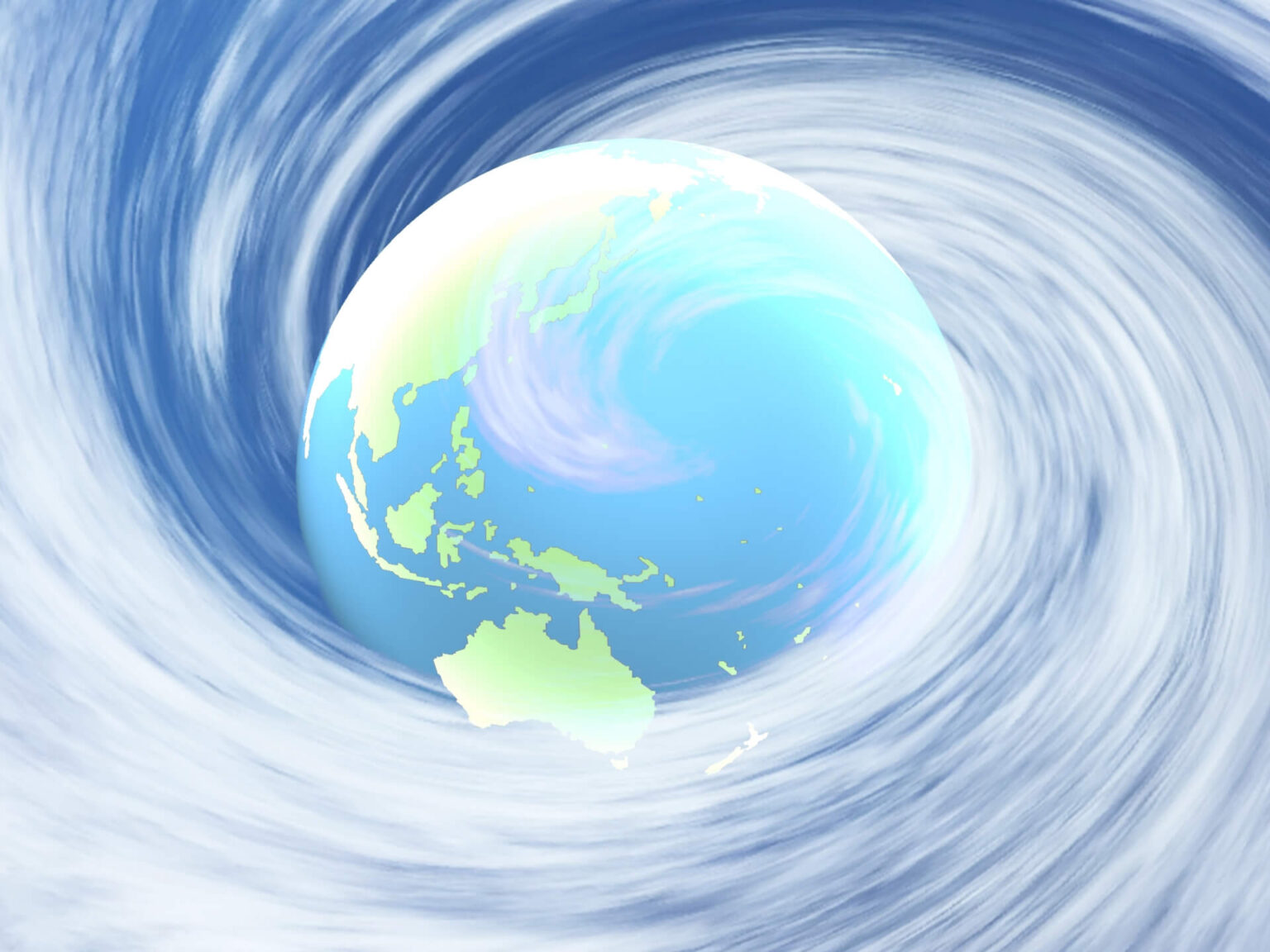
軒天の雨漏り まとめ

軒天の雨漏りは、放っておくと天井や屋根裏、壁内部にまで水が浸入し、住宅全体の劣化を早めてしまう原因になります。とくに目に入りにくい軒裏からの水の侵入は、発見が遅れやすく、被害が広がりやすいのが特徴です。
雨漏り対策には、まず正確な調査と原因の特定が不可欠です。その上で、部分補修だけでなく必要に応じた交換工事や、通気性・排水性に優れた有孔ボードの導入が、根本的な解決につながります。
また、修理後も定期的な点検と清掃を怠らず、台風のあとは必ず異常がないかをチェックする習慣をつけることで、住まいの寿命を確実に延ばすことができます。住宅の安心は「見えない箇所のケア」から始まります。軒天にもきちんと目を向け、雨漏りのない快適な住まいを維持していきましょう。
「屋根雨漏りのお医者さん」は雨漏り修理の専門業者!
「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏り修理の専門業者として住宅や建物のさまざまな雨漏りトラブルに対応しています。
屋根だけでなく、ベランダやバルコニー、外壁、窓まわり、サッシ、天窓など、建物の構造全体を見渡しながら原因を丁寧に調査し、最適な修理方法を提案・施工しています。特に原因調査に力を入れており、目視だけでなく、必要に応じて散水調査など詳細な診断を行うことで、表面化しにくい内部の雨漏り原因も見逃しません。
在籍しているのは、一級建築板金技能士や屋根診断士といった有資格者で、豊富な現場経験をもとにした高い技術力と判断力が強みです。調査から見積り、施工、アフターサービスに至るまで、すべてを一貫対応する体制が整っており、外部業者に委託せず、自社で完結するため、品質管理も徹底されています。
また、火災保険を活用した雨漏り修理の相談にも対応しており、申請のための現場写真や書類作成のサポートも行っています(※保険適用の可否は保険会社の判断によります)。戸建て住宅だけでなく、マンションやアパート、ガレージ、工場、店舗など、さまざまな建物の実績があり、法人やオーナー様からの依頼も増えています。
「屋根雨漏りのお医者さん」は、地域や規模にとらわれず、全国で対応を進めており、信頼できる職人ネットワークを活かして、各地域で迅速かつ丁寧なサービスを提供しています。お問い合わせは電話やLINE、メールフォームから可能で、初めての方でも相談しやすい体制が整っています。
長年の実績と、誠実な対応、高い技術力により、多くのお客様から厚い信頼を得ている「屋根雨漏りのお医者さん」は、雨漏りに悩むすべての方の強い味方です。どこから雨が入っているのかわからない、以前修理したのに再発してしまったという方も、まずはお気軽にご相談ください。調査・見積もり無料で行っております。













